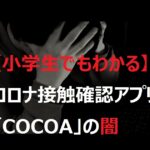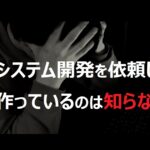あ〜あ、またワクチン予約システムでトラブルのニュースやってるね。
うーん、起きるべくして起きてるからなあ…

ええー?国の大事なシステムなのに!?
そもそも国のシステムじゃないし、闇が深いんだよね。

以下の記事でも紹介していますが、コロナ関連のシステムトラブルといえば「COCOA」が有名ですね。
今回はそのCOCOAよりも重要なコロナ関係のシステムトラブルについてお話します。
ワクチン予約システムは国のシステムではない。
コロナワクチンを管轄しているのは厚労省ですが、予約の受付自体は各自治体におまかせです。
V-SYSというワクチン管理システムは国で構築するから、接種の予約はコールセンターでやるなり、WEBシステムを作るなり、それぞれの市区町村の好きにしていいよ〜という状態でした。
各自治体は混乱したでしょうね。いずれかを選ぶにしろ、両方選ぶにしろ情報を管理するシステムは必要です。
ファイザー社のワクチンが特別承認されたのが2021/2/14で、2021/4/12から高齢者への接種が一部の自治体で開始されました。
この期間わずか2ヶ月です。
実際は承認前から動き出していると思いますのでもう少し期間は増えるとは思いますが、各自治体はこの期間で予算の補正や業者選定、要件の整理と発注、受け入れ検証を行う必要があります。
実際にシステムを開発するT企業がシステムを作り上げる時間はもっと短くなります。
これをビジネスチャンスと捉えた企業は早期にシステムを構築し、バラマキ販売できる姿勢を整えたりしていますが、そうではない企業にとっては世の中への影響度や色々なリスクを踏まえると、美味しい案件であるとは言い難かったと思います。
このように、それぞれの自治体が別々の業者に独自のシステム開発を依頼しました。
もう管理や運営に差があったり、トラブルになりそうなのは目に見えてますね。
実際に何が起きているのか?
大きく2つに分類することができます。
ひとつめは、アクセス過多によるシステムダウン、ふたつめは設定ミスや単純なプログラムのバグです。
アクセス過多によるシステムダウン
考えられる原因は2つあります。
まず、単純に想像力が足りないことです。
例えば接種券を10万人送ったとして、そのうち何人がWEBシステムにアクセスすると思いますか?
最大でも10万人と考えていれば良いでしょうか?
いいえ、そうではありません。
接種券をもっている対象者だけがアクセスするわけではありません。
システムが混雑することくらい誰でも予測がつくため、複数のデバイスでアクセスを試みるユーザーもいるでしょう。
少しでも予約の可能性を向上させるために、家族や知人に手伝ってもらうこともあるでしょう。
世間でも関心が高いシステムのため、住民以外やマスコミも興味本位でアクセスするでしょう。
そういった色んな要素を考慮してアクセス数の仮説をたてて、それに耐えられるシステムを用意したり、確実に耐えられる人数しかアクセスを受け付けない仕組みを導入する必要があります。
結局そこまで想像力が足りていなかったのでしょうね。
どれくらい世間が関心があるのか、認識せずに進めてしまったわけですね。
もうひとつ、考えられる原因は、時間がなかったことです。
十分な想像はしていた、予測はできていたにも関わらず、無茶な要求のために必要な仕組みを導入することができなかったり、十分なテストができなかったところもあるでしょう。
とにかく一刻も早く、システムを世に出してワクチンの予約を開始する必要があったからです。スケジュール最優先だったのが大きな理由です。
設定ミスや単純なプログラムのバグ
予約枠以上の予約を受け付けてしまったり、短い接種期間で予約を取れてしまったりというシステム障害の報告が出ています。
仕様が明確ではない見切り発車の状態で業者へ開発の発注してしまった自治体側に落ち度があるケース、十分なテストができていなかったIT企業に落ち度があるケース等、原因は様々だと思いますが、どちらにしろ時間がなさすぎたことが大きな要因と考えられます。
また、クラウドサービスの障害によって影響があった自治体もあります。
有名なSalesforceというサービスが5/12にダウンした事件があったのですが、このSalesforceを使ってワクチン予約システムを作っていた自治体はその間システムが理由不可になったはずです。
先に書いたV-SYSもSalesforceで作成されているので業務に影響があったみたいですね。
誰が作ったの??
通常、公共系の業務委託は競争入札が一般的です。
逆オークションですね。このシステムいくらでできますかー?と投げかけて一番安かった業者が選定される仕組みです。
ただし、理由がある場合は随意契約、つまり、自治体が業者を指名して発注することも認められています。
競争入札にしている自治体もありますが、時間がかかることから随意契約にしている自治体も多くあります。
この場合、どのような業者を選ぶのでしょうか?
もちろん知らない会社のわけはなく、何らかの業務委託を行った実績のある業者を選びます。
では、その指名された業者は、本当に今回の要望のシステム構築ができる企業なのでしょうか??
できないかもしれません、が、問題はありません。
できる会社に外注すれば良いだけです。
そう、多重下請け構造の闇がここでも爆誕しているわけです。
(参考)
責任の所在が曖昧になるIT業界の悪いところが当たり前に活用されてしまっているのです。
自治体→1次請け→2次請け→3次請けの構造で3次請けの会社が仕様の確認をしたい場合、3次請けから2次請けに確認をし、伝言ゲームで2次請けから1次請け、1次請けから自治体と自治体に質問がたどり着くまでがとても長いです。
また、回答のときもその逆が発生するので、出した質問の回答が返ってくるまでの時間ロスはとてつもないです。
ただでさえ開発期間が短いのに、です。
どんどん追い詰められていくわけですね。
電話 vs ネット 予約が取りやすいのはどっち?
電話とインターネットではどちらの予約が取りやすいのでしょうか。
すみません、わかりません…。
インターネットの予約サイトではシステムダウンさせないために、一定数のアクセスしか認めない仕組みを導入している場合もあります、
また、同じようにNTTも電話制限をかけて、ネットなどの代替手段を活用してほしいとの発表もありましたが、WEB側からすると「落ちたら困るからそんなにアクセスしないで電話にしてよ〜」と思いますよね。
どちらも規制をかけているので、どちらを使用したら良いのかわからなくなってきますよね。
ネットのほうが回転率は早いのでネットな気もしますが、制限がかけられていたり、すぐに枠が埋まってしまうこともあるので、気長に電話を待つのが確実なのでしょうか…。
SNSでは、ネットでトライしながら、電話をしていたら電話がつながったという声も散見されます。
これが全国民が接種対象者になったときにどうなるのか、、、恐ろしいですね。
ーーーーーーーー
いかがでしたでしょうか。
自治体が悪い、IT企業が悪い、もちろんどちらもありますが、真の原因は十分な時間がないのに、各自治体に丸投げなことだと思います。
そんな中でも平然と存在するIT業界の闇のひとつの多重下請け構造もあります。
起きるべくして起きている問題だとも言えるのではないでしょうか。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。